2013年03月20日
防災フォーラムへ
3月20日、今日は春分の日でお休み。皆さん、いかがお過ごしでしょうか? ワタシは、地元行事をいくつか回らせていただいた後、お隣伊賀市の大山田産業振興センター(どんぐりホール)で開催の「防災フォーラム」(三重県主催)を聴講に行ってきました。三重県防災対策部から「三重県新地震・津波対策行動計画」中間案について説明があった後、三重大学大学院工学研究科の川口諄准教授から、「新たな防災・減災対策に向けて」と題して講演をいただきました。
東日本大震災からわずか2年にもかかわらず、すでに風化や忘却が進み、防災意識、危機意識の低下が心配されていますが、川口准教授のお話は、難しい理屈ではなく、心理的にうまく防災意識、危機意識を植え付けてくれる、いいお話でした(早口の関西弁の話術の影響もあるかもしれませんが)。
たとえば、「ガンで亡くなる人の確率は6.8%、交通事故で亡くなる確率は0.2%、それでも人は保険に入ったり人間ドックに入ったりと対策を講じるのに、震度6以上の地震が起こる確率は87.4%あるのに、人々は何も対策を講じようとしない。」「自宅の耐震工事に180万円はとてもかけられない、そんなお金はないと言う人が、帰っていくときにプリウスにさっそうと乗っていく、なんておかしい」と。昨日は、想定される南海トラフでの巨大地震を最大級に見積った場合の被害想定が発表されたばかり。いま一度、自助、自分たち自身で自らの命を守りきる意識と行動が求められています。
投稿者 boss_blog : 22:41 | コメント (0)
2012年02月07日
がんばろう!! ふくしま
会派「新政みえ」の県外調査の報告の続きを。今回の調査の後半は、「福島被災地応援ツアー」ということで、企画しました。前述のように、今回の企画は福島市観光物産協会の皆さんに、お世話になりました。ご協力、本当にありがとうございました。また、同じく、福島市、相馬市、伊達市、二本松市、相馬市観光協会の皆さまにもお世話になりました。心から感謝申し上げます。

調査二日目の午後最初は、福島市役所を訪問させていただき、被災当時の状況から、除染計画、さらには福島市の復興計画等について教えていただきました。津波被害のない地域ですが、3.11には震度6弱の揺れに襲われ、人的被害や家屋の被害を受け、一時ライフラインも途絶える状況となりました。さらに、原発の影響を受けて市民の健康に対する不安もあり、また、風評被害で特産の果樹や観光の温泉地が影響を受けるなど、まだまだ震災の爪痕を残しています。

除染計画では、計画期間を5年、重点期間を2年とし、今後2年間で市民の日常生活環境における空間放射線量を市内全域で1マイクロシーベルト/毎時以下にすることを目指しています。ただ、除染に伴う土壌の仮置き場に苦労しているとのこと。また、市外への避難市民数が約5,600人、一方、1万人を超える避難民を市外から受けているという現実もあり、コミュニティ形成にも配慮がいるようです。

二日目午後の後半は、福島市内の温泉地、土湯温泉に向かいました。ここは、福島市内でも最も汚染の心配のない地域なのですが、建物の被災や風評被害で観光客が減少し、厳しい環境に苦労されているところ。16軒あった温泉旅館も6軒が、建物の被災等で倒産したり長期休業したりしています。写真は、土湯温泉の一部。雪景色の中に浮かぶ、すばらしい温泉地でした。(宿泊させていただいた山水荘さん、ごめんなさい。宿の外観写真をとりそこねてしまいました・・・あしからず)

宿泊地である山水荘の渡邉社長に、「土湯温泉復興への道」と題して、講演をいただきました。渡邉社長は、土湯温泉観光協会の会長であり、NPO法人・土湯温泉観光まちづくり協議会の会長でもあります。渡邉社長からは、平成の初めころから、温泉町のまちづくりに取り組んできたこと、震災時は電気が止まる中、3日間、宿泊客を預かっていたこと、その後は機動隊を預かったり、浪江町や南相馬市の避難民を夏まで受け入れてきたこと、などを聞かせていただきました。風評被害については、テレビの映像で住民がマスクをしている映像ばかりを流すので、どの地域でもそういう状態と勘違いされるとのこと。それでも、なんとか土湯温泉のまちを復興させようと、「土湯温泉町復興再生協議会」を立ち上げ、温泉蒸気と温泉熱水を利用したバイナリー発電にチャレンジするなど、復興再生に取り組んでいく熱い思いをお話いただきました。

上の写真右が渡邉社長。左が、そのあとお話いただいた、「渡利の子どもたちを守る会」の菅野さん。菅野さんたちの守る会は、除染作業等での被爆から子どもたちを守るため、また、ストレスいっぱいの子どもたちに少しでもリラックスしてもらおうと、土湯温泉等の温泉旅館と協力しあい、格安滞在できる「わたり土湯ぽかぽかプロジェクト」に取り組まれています。渡利地区は比較的線量が他の地域より高めであるため、子どもたちの健康を心配されています。市外県外に移る家族もあるようです。プロジェクトの資金は一般からの寄付で成り立っているそうですが、経費が多く必要なので、今後は海外からも寄付を受け付けたい、また、合わせて、土湯温泉の安全もPRできたら、とのお話でした。

調査3日目は、相馬市にお伺いしました。相馬市は福島市と違って沿岸部であり、大津波の影響を直接受けた地域です。死者行方不明者458人、人口は震災後3,000人減少しています(人口36,823人)。震災時は、原発事故による風評被害で、物流がストップしてしまい、被災地から逆にトラックを手配して取りに行ったそうです。

相馬市の沿岸部を案内いただきました。海岸に近いところは、一面何もない状態が続きます。見えるのは作業のダンプだけ。

広大な平地で、ボランティアの方でしょうか。ごみ拾いの作業をされています。田畑のあとでしょうか。

このあたりの水田は、すべて大津波が来たところなので、塩分を含んで表面が白くなっています。今年は作付けは無理だろうとのこと。来年に向けて、改善作業が取り組まれるようです。

海が間近なところでは、まだ、大津波に呑まれ被災したそのままの建物も。

漁港も大津波に呑まれ、施設関係も基礎だけを残し、何も残っていません。

調査の締めくくりは、震災を乗り越えて、民宿業を再開された相馬市松川浦の「亀屋」さんにお邪魔しました。とにかく復興再生にかけるというご主人の姿に、エールを送りたい気持ちでいっぱいでした。ありがとうございました。
投稿者 boss_blog : 18:52 | コメント (0)
2012年01月08日
想定外 NO.824

※連合三重・新春旗開きでの山田町商工会 佐藤専務の講演(津都ホテル)
4日から役所の仕事も始まり、また、今年は地元の工場も同時期に動き始めましたね。ワタシはと言えば、地元商工会議所の新年祝賀会や連合三重の新春旗開き、消防出初め式などなど、年始の恒例行事が続きます。連合三重の旗開きでの講演会で、東日本大震災で被害の大きかった岩手県山田町の商工会、佐藤専務のお話が印象的でした。震災から10か月たったけれども、大津波は今も人々の心に大きな爪痕を残している。大津波の中で、おまえだけは、生き残ってくれと父親に手をはなされた息子さんの話、一緒にいながら子どもを助けられず、精神的におかしくなってしまったお母さんの話、失礼ながら、助かったのにも関わらず、逃げる際に助けあうことがなく、互いに不信感が生まれてしまった夫婦の話、自殺者も多く発生しているようです。時の流れは、わたしたちをどんどん鈍感にしていきますが、あらためて心が痛む思いがしました。そして、佐藤さんが最後に言われた言葉が印象的でした。「ここは、東海・東南海・南海地震が予想される地域で、間違いなく来るといわれていますよね。だったら、想定外のことが起こったという言葉がでないようにしてほしい」と。行政もわたしたち住民も、たくさんやるべきことがある、そう強く考えさせられました。
投稿者 boss_blog : 22:54 | コメント (0)
2011年09月21日
ロウキ-去る NO.802
台風15号(アジア名・ロウキー)が、ようやく三重県から遠ざかりました。震災地の東北沿岸沿いを進んでいるということで、心配ですが、こちら名張は雨も上がり落ち着いてきました。人命に関わる災害は、ありがたいことに市内ではありませんでしたが、大雨の影響で県道奈良名張線(夏秋~薦生の間)で法面が崩れ道をふさいでしまいました。復旧には数日かかる見込みで、周辺地域の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

※土木事業者の皆さんの活動は、こういう際には、本当に頼りになります。


※作業にあたってくれる土木事業者の皆さんも、県職員の皆さんも、ある意味危険と隣合わせ。十分、気をつけて作業にあたってください。

※横を流れる名張川の濁流を見ると、恐怖感でいっぱいに・・・
☆三重県の事業市仕分けの動画(USTREAM)が、一部動きません。現場に行けなかった18日分の交通施策や観光関連のパートが、いつまで待っても「しばらくお待ちください!」です。使い方に問題あるのかなあ~誰か教えて!
→ カフェ メキシコ★ハナコ
※投票は1回のみよ!
投稿者 boss_blog : 22:31 | コメント (0)
2011年09月04日
少し落ち着きましたね NO.797

※滝之原から青山町に向けて、一部法面の崩壊により通行に支障がでている広域農道「伊賀コリドール」

本当にやっかいな今回の台風でした。全国で死者22人行方不明者55人、三重県南部、和歌山県、奈良県を中心に大きな被害がでました。記録的な雨量に、「想定外」とは言えない、今までの常識が通じない自然環境の変化を感じます。いろんな面で、災害対策の見直し作業が求められていますね。
さて、東北被災地での調査報告の結びに、個人的なまとめをしておきます。まだまだ、勉強不足ですが、東海・東南海・南海地震も想定される中ですから、少しでも今できることを進めておきたいと思います。
被災地調査のまとめ
◎支援に係る意見
・被災地ではガレキの片づけなど、まだ作業として残るものがあるものの、行政が直接支援するというよりは、三重ボラパックなどによる支援が継続されることが重要であり、県としては、経費も含め側面的に支援することが求められているのでは。
・今後、高齢者をはじめとする被災住民の心のケアが欠かせない状況を考えると、専門的なスキルをもったスタッフを長期的に派遣できるシステムづくりが必要と感じます。現地スタッフと派遣スタッフが協力、もしくは機能分担しながら進められるといいのでは。
・被災自治体へすでにバラバラに入ってしまった三重県の態勢を再編することは容易ではありませんが、派遣されるスタッフは入れ替わっていくわけですから、他県と話し合い、バーターできるところは調整してもいいのでは。
・被災自治体にとっては、復旧のみならず復興にも他の市町職員(特に専門職)の応援が必要です。平成23年度末以降の支援も視野に、長期的な派遣を財源手当ても含め、考えるべきかと。
◎今後の災害対策に対する意見
・今回、被災県の対応のまずさを指摘する意見が多く聞かれましたが、根底には、情報伝達、並びに共有のシステムが十分に機能しなかった点にあると考えます。県と市町、市町と各コミュニティ、地域住民との連絡手段を今以上に多重に確保することが求められます。現在のシステムの見直しが各自治体で行われるべきと考えます。
・津波に関しては、被災が想定される市町に対し、被災が想定されない市町を後方支援として複数ペアリングしておく必要があるのでは。実地訓練も必要です。
・地震、津波、風水害それぞれを想定しながら、三重県内の市町をお互いに支援するペアリングを県が主導で行っておいてはどうでしょうか。
・同様に、県内市町と他県の市町とのペアリングも、県が情報提供しながら、東西の距離間隔、人口規模、地形、移動ルート等を勘案し、進めていく必要があるのでは。平常時からの交流を行い、人的なつながり、システムの共有等が進めば理想です。
・被災自治体を後方支援する自治体への財政的支援策を国に求めていく必要があります。
・県内市町が被災した際には、現地へは権限をもった管理職以上が行くようにすべき。現地で判断し、県庁へも指示が行える態勢づくりを。他県への支援の際も同様である。
投稿者 boss_blog : 23:34 | コメント (0)
2011年09月03日
引き続き厳重警戒を! NO.796
台風12号(アジア名:タラス)の雨も、ようやく峠を越えたかな?まだ、油断はできませんが、現在のところまでは、局所局所では被害はあるものの、大規模な災害は、昨日の伊賀つばさ学園を除けば発生していないようなので、よかったです。このまま、天候が回復し、山も川も落ち着いてくれることを祈ります。
さて、今夜も調査報告の続きを。今回の調査で、ワタシ自身が一番伺いたかった調査先、遠野市です。岩手県沿岸部の大津波を想定し、早くから後方支援の拠点化を進めてきた遠野市。三重県も沿岸部の津波を想定すると内陸部であり、また関西と東海の結節点である伊賀地域は、後方支援の拠点としては最適ではと思っています。
~被災地での調査報告 その⑤~

※山田町内でのガレキ置き場。ちょっと見にくいですが、ガレキがいくつもの山となっています。

※遠野市役所の玄関です。静岡県だけでなく、大阪府、東京都等の現地支援本部もおかれているようです。東京大学や神奈川大学の名前もありますね。

※市役所庁舎(議場部分だったかな?)自体も被災している中で、丁寧にご説明いただき、誠にありがとうございました。
⑤8/5遠野市役所にて「遠野市の後方支援、静岡県現地支援調整本部との連携、静岡県の支援内容について」調査
説明:菊池保夫 岩手県遠野市総務部沿岸被災地後方支援室長 ほか
・宮古市、釜石市、大船渡市など沿岸市町へ陸路で約1時間、ヘリコプターで約15分で移動できる立地環境などから、遠野市は平成19年から「地震・津波災害における後方支援拠点施設整備構想」を進めてきた。市長は、県OBで、阪神淡路大震災のときは県の防災課長、現場経験の後、2年間で岩手県の防災計画づくりをした人である。4年前から訓練にも取り組んできた。平成19年の岩手県総合防災訓練、平成20年の東北方面隊震災対処訓練(みちのくALERT2008)では、市の運動公園や早瀬川敷地で、自衛隊・警察・消防・医療機関・住民などと合同の訓練を実施し、宮城県沖地震に備えてきた。
・構想の概要 ◎地震や津波などの被害に対し、防災ヘリコプターで沿岸市町へ約15分で移動できること。地質が花崗岩で安定していることなどから、後方支援には遠野市がふさわしいこと。◎支援物資の収集、仕分け、搬出作業のための施設が必要なこと。◎各種支援隊の仮眠場所、宿泊場所を計画していること。
・津波被害が現実になった。地震発生から約11時間後の3月12日、大槌町から歩いて一人の男性が、救援を求めてきた。このSOSをきっかけに、沿岸被災地域への後方支援活動を本格的に開始した。
・後方支援に市民の理解を得られたのは大きかった。市民に感謝している。
沿岸のためにお金を使ってみたいな非難はなかった。背景には訓練を見てきたこと、遠野市内の倒壊はゼロ、死者もなく、高齢者もすべて確認できたなど、
よって後方支援に専念できた。
・ラジオしか情報がなく、被災地は連絡がつかず。やはり重要なのは情報。岩手県からも情報入らない。結局、毎日、被災地へ行ってきた市職員が報告する情報が頼り。1日2回、市役所内で会合と情報交換を(職員集会を6時と20時に実施)。4班20人体制で支援を。二度の訓練が生かされた。
・遠野市庁舎も被害を受けている。被害額、約32億円。
・遠野運動公園に自衛隊、消防隊等が集結した。スピーディに対応できたのは、以前の訓練のおかげ。
・被災地からの患者受け入れ211人。被災地への救援物資の搬送250回。14万人分のおにぎり用意。避難者の受け入れ、個人宅避難の情報収集。体育館である物資拠点を開放する。入浴施設も無料開放し、入浴支援を。
・後方支援とは何をしたらいいか?ここを拠点に支援する団体の支援を行うこと。消防隊は実際入りきれなかったので、高校の体育館を急きょ借りた。自衛隊は自前でテントも持ち、自己完結型だが、消防隊は持っていない。寒い時の行き場が必要になる。警察隊も同じで、しかも、県警ごとに来る。ホテル、旅館はキャパ600人のみ。144のコミュニティセンターをすべて開放してもらった。100施設は使用した。今も市内に避難者400人あり。
・静岡県は、いち早く来てくれた。動きが早かった、しかし、岩手県は静岡県何しに来た?という具合だった。静岡県は、自分たちで被災地歩いてくれた。 遠野市に拠点おきたいと要請があった。静岡空港も◎ 飛行機で物資輸送 車10台すぐに来た。
・物資支援は、縦のつながりではなく、横のつながりで出来た。42市町の友好の輪が。遠野市に送れば届くと思ってもらえた上、市民ボランティアも協力してくれた。
・遠野市内を拠点としたボランティアは約250団体。1日最大1109人の 宿泊が(7/25)
・三陸文化振興プロジェクトとして、献本を実施中、15万冊集まった。分類整理中で、整えば学校に送る予定。公立図書館は、そのあとに。
・医療に関しては、産科がないなど元々厳しい地域。モバイル検診を遠野市で初めているが、被災地域にも広げようと考えている。
・後方支援がすべてうまくいったわけではない。想定はしていたが、食料備蓄が十分できていなかった。発電機や投光機もなかった。対口支援は、あらかじめマッティングをしておけば、もっとよかった。遠野市3万人では、沿岸市町すべてをカバーするのは無理がある。県のリードで、ペアリングをしてもらっていればよかったかと。
・後方支援に財源こない。制度化が必要で、全国どこでも必要。そうすれば、後方支援がやりやすくなる。人件費別で2億5千万円ほど持ち出しか。3月中は、職員400人のうち、部局で使える人数200人、そのうち50人くらいを投入してきた。
・震災後、市内スタンドをストップさせてストックを調べ、支援車両にだけ給油をするようにした(チケット制にして統制した。身の危険も感じたくらい)
・役所内、支所内、すべての灯油を集め、独居老人に配った。役所の人間は寒くてもジャンパーで作業。大船渡市では凍死?と聞き、県庁にTELしたが、八戸にタンカー来るからといった対応。
・県との連携は×。知事の権限で自衛隊、警察(警察庁)、消防(自治体)
動かせる。分身くるかと思ったが、来なかった。県に現地で対策本部をつくるべきと進言し、やっと出来たが、権限与えていなかった(連絡員レベル)。せめて副知事クラスが来てほしかった。あるいは、振興局部長に権限与えるとか。
投稿者 boss_blog : 22:23 | コメント (0)
2011年09月02日
タラス襲来!! 厳重警戒を
台風12号(アジア名:タラス)が接近しています。市内あちらこちらで大雨や強い風の影響で被害がでています。長時間にわたり大雨が続いていますから、がけくずれや浸水に対して厳重な警戒が必要です。台風情報や地域の情報を、それぞれの立場でしっかり受けれる態勢を整えてください。まもなく暴風域にはいります。

※テレビのニュースでも放送された、県立つばさ学園の敷地崩落現場の様子。ケガがなくてよかったですが、復旧は、この大雨がおさまらないと、かかれない状況です。

※同上

※宇陀川の水位も随分あがってきました。2年前にも道路まで水が越してきた赤目中学校前。心配です。市からの情報に十分注意してください。
投稿者 boss_blog : 22:08 | コメント (0)
2011年09月01日
タラスが来る! NO.784
台風12号(アジア名:タラス)が接近しています。四国から近畿地方を直撃しそうな雰囲気ですね。しかも、今年の特徴なのか、政治の影響なのか、進むのがとにかく遅い!ゆっくり!自転車並みの速度です。雨、風のダメージを受けやすい状況になるので、動向が心配です。また4日は、名張市で三重県の総合防災訓練が行われる予定なのですが、これも運営が心配です。一応、警報が出されると中止となる予定ですが、事前の準備等、関係者の皆さんには、大変ご苦労をかけそうな事態です。
さて、引き続き報告を。~被災地での調査報告 その④~

※「みえ災害ボランティア支援センター」が当初から応援してきた「山田町災害ボランティアセンター」
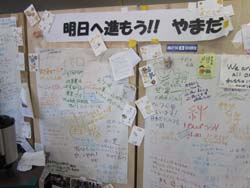
※応援するみんなの気持ちがいっぱい!

※忙しい中、時間をいただいてホントに恐縮でした。
④山田町内のB&G海洋センターにて 「山田町災害ボランティア・センターの活動状況について」調査
説明:福士 豊 山田町社会福祉協議会事務局長
阿部寛之 山田町社会福祉協議会事務局事業推進係長
・山田町災害ボランティアセンター活動実績= ボランティア受付件数、個人2,145人、団体833団体で10,773人、合計12,918人、ボランティア派遣件数1,870件、派遣人数14,472人
・主な活動=物資荷物の積み下ろし、物資仕分け作業、ガレキ回収、イベント準備・補助、サロン活動、写真洗浄・持ち主返却、ニーズ調査、調理補助、ポスティング、炊き出し補助、バイク修理、電気設備点検、ボラセン内片づけ、電話接続手伝い、ボランティアへの健康チェック、土嚢積づくり、マッサージ(避難所)、配食補助、慰霊祭準備、避難所での散髪、一輪車パンク修理、物資運搬・搬入、引越し(避難所から仮設住宅)、物資搬出入・仕分け、屋外作業・清掃(住宅、敷地等)、弁当配布、仮設住宅物資搬入、子どもの遊び相手
・協力派遣社協(ブロック派遣社協)
静岡県社会福祉協議会及び静岡県内各社会福祉協議会→センター運営スタッフ
長野県社会福祉協議会及び長野県内各社会福祉協議会→センター運営スタッフ
・その他協力社協 愛知県東海市社会福祉協議会 →地域福祉事業スタッフ
・三重県の社会福祉協議会は隣の大槌町に入っているかと。
・三重県のボラセンには、ボラパックを協力いただいた。一番長く継続して三重にはやってもらっている。地元社協の人員、手法、足らない部分を三重がスタッフとしても協力してくれた。緊急雇用でスタッフ(15人)が雇えるように6月中旬になったので、運営はスムーズに。その時点で運営から現場に移ってもらった。重機入ったあとの清掃やその他、写真の洗浄、チラシのポスティング、調理補助などなど。ガレキは今後なくなっていくと思うが、以降は被災者支援にどう取り組むかが大きな課題で、現在検討中だ。
・4/10にセンターを立ち上げた。立ち上げに時間かかったのは、センターに出来る場所がなかったから。ここB&Gも当初は遺体安置所でもあった
・スタッフ4名、1カ月常駐。マッチィングの要。4/28にはボラパックがスタート。三重社協は大槌町に入っているが、ボラセンは山田町に入っている。
社協スタッフは、市町のローテーションで賄う
・仮設住宅が進み、避難所が減少傾向に。避難民がばらばらに離れていく状況にあり、避難所に残った人は淋しい気持ちに。一方、仮設住宅にはコミュニティがないという問題も。そのため、仮設住宅でサロン活動を始めた。毎水曜日 2か所で実施。顔を見せない人は孤立していくことも。コミュニティを担ってくれるキーパーソン出来ればいいが。サロン活動は地元のスタッフにしか出来ない仕事になる。長い付き合い、顔と顔、方言も含めて。しかし、一方で人員が人足りない。ただ、専門性が必要になり、また長期の活動にもなる。スキル+資質も重要なポイント、なかなか難しい。
投稿者 boss_blog : 21:23 | コメント (0)
2011年08月31日
被災地での調査報告その③ NO.793
台風が接近してきましたね。はじめの予報では、東の方に向かっていく感じでしたが、まっすぐ北上してきましたよ。ヤバイのではと、心配しております。皆さんも、十分に警戒を!!
それでは、続きです。また、念のためですが、少々非難めいた表現もでてきますが、できるだけ被災状況を知るためにも、聴き取った通りに書かせていただきました。関係者の皆様には悪しからずご了承を。

※町長さんや、数十人の職員さんが亡くなられたり行方不明になっている大槌町役場。言葉がありません。心からご冥福を。

※山田町もガレキが随分片付いています。目の前に広がる空虚な空間。これも言葉がありません。

※対照的に」、山田町役場は、少し高台になるので、下部を除いて難をのがれています。役場や職員さんの存在のあるなしは大きいです。
③8/5山田町役場にて「山田町における静岡県の支援について」調査
説明:沼崎喜一 岩手県山田町長
白戸 山田町危機管理室長
山田町の被災状況は(8/3現在)、死者702人、行方不明83人、避難者561人(22か所)。
沼崎山田町長のお話~
・静岡県等の応援あって、何とか日常業務をこなしている状況。北海道ほかの支援は7月いっぱいで撤退予定。主に、避難所の世話を支援いただいた。仮設の移転準備もようやく進んできた。
・数年前にあった、遠野市からの後方支援のお話は、初めあまりピンとこなかったが、遠野市長自ら熱心に説明にまわってこられた。
・被災後は、大槌町の住民が歩いて遠野市に支援を求めにいって、はじめて情報が伝わったという経緯。衛星回線が伝わらなかった。静岡県の支援は抵抗なく受け入れた。岩手県自体が混乱していた状況。岩手県は沿岸部からの情報待っていたようだが、町は大混乱の状況。岩手県自身が現地に直接、足を運ぶべきだったと思う。途中から不満聞いてもらい、支所のある宮古から県が来るようになったが。
・瓦礫撤去は宮古以南では一番進んでいる。町での負担は無理だが、国の回答は待っていられないので、見切り発車した。結果オーライで国が全額近く負担してくれることに。
白戸室長からの説明~
・自衛隊も入って 津波対策の訓練、毎年行ってきた。
・津波+火災の発生に対し、道がなくなっており、消防の消火活動が不可に。
・岩手県の防災無線は話中に。たまに繋がるが・・・FAXもNG。県が直接動いていない。訓練では現地に行く予定にはなっていたが、自治体が被災し機能していないと考えていなかった。
・被災自治体で何ができるのか?何も出来ないことに気づく。静岡県は「軽トラ5台もってきます!」と言ってくれた。「何が必要か?」ときく県はいらない。水、食料、暖房、被災地現場に必要なものは明確だったはず。
・避難所では、物資をおろす職員がいない。被災地職員は、住民のけが対応、行方不明者探し、連絡調整等で、全く動けない。物資が届かないのではなく、降ろすのに精いっぱい。持ってきてくれるだけではダメ!避難所の人の手にまで届かないと意味がない。それだけの人員が必要。県の対応は×。海上自衛隊は提供できる備品リストを出してくれた。静岡県も同様にしてくれた。気持があるかどうかだ。
・民間ボランティアは感謝している。でも1週間で帰ってしまうので残念。NPOによっては、実績ほしさのところもあった。
ポイント
※県と連絡ができるかどうか
※町内と連絡がとれるかどうか
各支部と連絡とれると安心感に。電気、電話、携帯全部がダメになった。
TVも電源がダメ、AMラジオもダメ、役場内は暗いままで、仕事が出来ない状況に。海上自衛隊は、3/11の16:00には来てくれたいた。
・業務は、途中から応援スタッフに移した。仮設住宅準備や義捐金処理に追われる。他市町の職員に入ってもらいギリギリもっている。大槌町は、亡くなった職員多く、機能できていない。
・政府の現地対策本部は盛岡市に。山田町には、岩手県が直接入っていない。 支所対応のみ。盛岡(県庁)は、津波の危機意識ないのでは。一方、静岡は県内の8割が被災する可能性があり、危機意識が高い。
・町職員は、自らも被災しているが、何とか自分たちでやらなきゃと思っている。他の市町職員の応援を頼もうとしない、受け入れない。そういう面での心のケアも必要かと。
・山田病院は、仮設で対応しているが、入院はできない状況に。
投稿者 boss_blog : 18:40 | コメント (0)
2011年08月30日
被災地での調査報告その② NO.792
テレビのどのチャンネルをまわしても「ドジョウと金魚」の話ばかりですが、何はともあれ民主党の新代表に野田さんが決まりました。三人目の正直!?といった見出しもおどっていましたが、とにかくこの際落ち着いた政治を望みたいところ。特に、どの報道も触れていますが、震災対策や原発問題、経済復興など、国難とも言われているこの状況下で政治を進めるには、「ねじれ国会」がそのままでは、どうしようもありません。制度改革も含めて、政治が前に進む手法、知恵を出し合ってほしいと思います。
相変わらず、ちょっと?長いですが、報告の続きを。また、念のためですが、少々非難めいた表現もでてきますが、できるだけ被災状況を知るためにも、聴き取った通りに書かせていただきました。関係者の皆様には悪しからずご了承を。

※宿泊した釜石市の駅前商店街の被災の模様です。

※1階は津波の襲来で激しい損傷状態です。夜の到着でしたが、信号も電気もついていませんでした。

※釜石市から山田町へ抜ける途中。大槌町あたりです。後ろは、被災した学校のようです。

※ここに町があった・・・・・ガレキ撤去が随分進みました。足元をみると、建物の基礎が・・・たくさんの家が建ち並んでいたところでしょう。今は、まるで荒野のよう・・・
①8/4 静岡県の現地対策本部のある遠野市浄化センターにて 「静岡県の被災地への支援について」調査
説明:小川英雄 静岡県危機管理部理事
・静岡県は、いち早く被災地に現地支援調整本部を設置し、現地のニーズ調査から、支援物資の提供、さらには派遣職員の受け入れ態勢づくりに積極的に取り組んできた。
・知事会からは岩手に物資支援してとの要請あり。ならば、全面的に入ろうと決断した。ここ遠野市は、扇の要の位置にあり、ここに本部をおくことにした。東北人は、どちらかというと閉じてしまう人柄なので 地元遠野市の人と一緒に行動することがベターと判断。中国四川省とは友好関係にあったので、対口支援について聞き及んでいた。
被災地の支援にあって取り組んだ基本的な考え方
・被災者の立場にたち、被災自治体の手となり足となった活動する
・日々変わる被災地のニーズに的確にする
・混乱した被災地では、「何が必要ですか?」ではなく、「こういうことができる」と、具体的なメニューを提示する
・先遣隊11名(3/19~3/26)
主な活動=岩手県内の被災地を調査、主な支援先を大槌町、山田町に、被災した沿岸市町を支援する遠野市と連携 支援物資=スズキ自動車から提供受けた軽トラック10台、毛布、水、非常食
・第1次隊20名(3/25~4/1)
主な活動=遠野市浄化センターに現地支援調整本部を設置、大槌町、山田町、遠野市の物資拠点運営支援、遠野市災害対策本部に要員配置 支援物資=生野菜、果物、米、粉ミルク、下着、靴等生活必需品
・第2次隊26名(4/1~4/9) 主な活動=物資拠点運営支援を継続、被災市町の行政事務の応援ニーズ把握(一部事務を応援) 支援物資=野菜、果物、調味料、行政事務用品
・第3次隊26名(4/9~4/16)
主な活動=物資拠点運営支援を継続、行政事務の応援を開始 支援物資=子ども用文房具
・~現在は、第19次派遣隊24名
・知事会では、重なり避けるための調整は必要だが、振り分けは無理。市長会も含め、事務的な作業をするマンパワーはない。
・静岡県庁の危機管理部のヘッドが自衛隊出身者で、これだけの大災害だと現地に入ってみないとわからないと判断し動いた。遠野市は、以前から後方支援の訓練も行っており、被災地←→隣の自治体←→外の自治体へ という支援の流れを考えた。
・支援本部は4週間後に立ち上げ、県1/2市1/2の人員構成割合で派遣した。 現場は、罹災証明の手続きなど、市町の職員がほしいから、県内市町にもお願いした。人口割り等、構成割合の調整は静岡県が行った。(初めは、市長会、町村会に頼んだが、事務的なキャパがなかったので)
・財源については、4月は交付税でもらった。ありがとう、と言ってもらえる時期まで、9月末くらいまでは現地での支援を続けたい。
・地域経済の復興を考えると、物資については、ある時期からは地元で買ってあげる、調達してあげることも重要。
・静岡県のボランティアセンターも、同じ場所、遠野市浄化センターに設置している。仮設住宅に入居すると支援が途切れるので、これからは、ボラセンの役目が大きくなるのでは。
・後方支援拠点となった遠野市の存在は大きかった。後方支援の体制づくりに積極的に取り組んできた市長の存在は大きい。
投稿者 boss_blog : 22:52 | コメント (0)
2011年08月28日
被災地での調査報告その① NO.791
今年の夏休みも、まもなく終わりですね。いい夏が過ごせたでしょうか?宿題に追われている子どもの手伝いをしてる(させられている?)親もこの時期ありかも。そんなワタシの宿題は、今夏もたくさんの調査に行かせてもらいましたが、その中から、所属する東日本大震災に関する復旧・復興支援調査特別委員会で出向いた東北の被災現場と自治体の調査報告書をまとめること。調査先は、5か所ありましたが、順にレポートしておきます。

①8/4 宮城県議会にて 「宮城県の初動対応について」調査
説明:佐藤宣行 宮城県総務部危機対策課長
東海林清広 副参事兼課長補佐
8月3日現在での宮城県の被災状況の概要は、死者9,275人、行方不明者2,437人、家屋の全壊70,105棟、半壊67,014棟、避難所数236施設(ピーク時は1,183施設)、避難者数8,895人(ピーク時は320,885人)。ライフラインの復旧状況については、電気は、津波の被害を受けた地域を除きすべて復旧、水道は、津波被害により11市町で給水支障(未復旧率約4%)あり、ガスは、被害が甚大な地域を除きほぼ復旧、現在は気仙沼市で供給に支障あり。応急仮設住宅は、17,276戸(15市町)を完成引き渡し済で、8月中旬を目標に累計2万2千戸の完成を目指す。災害廃棄物は、概ね1,500万tから1,800万t(土砂を除く)、1年以内に現場から一次仮置き場に撤去し、二次仮置き場において概ね3年以内(平成23年度末)を目処に処理。街を元に戻すことは出来ないので、新たな地域づくりをゼロベースで考えていきたい。夜間は30~40分で避難できないから、どうしても住居は高台にしたいが、莫大な費用がかかる。特に、気仙沼市や石巻市は平地が少なく、仮設も厳しい環境になる。
(1)これまでの防災計画の検証
◎県の初動態勢等と課題
・地震と津波は別物。宮城県沖地震に備え、アクションプランをたて官民挙げて施設の耐震補強、道路整備等実施してきた(震災対策推進条例もH20年に制定)→ 一定の成果はあった 地震による死者は3人で、他はすべて津波による死者。
・津波では死者・行方不明者合わせ約12,000人。M7.4~8.0が最大と想定してきたので、ある程度は防げると考えてきたが、実際はM9.0(世界4番目)。津波は被害想定調査の2~3倍の高さ。地震から津波襲来まで、約40分~60分。津波の破壊力は巨大であった。
・ハードには限界があり、減災へ向けて避難意識の醸成が重要。
・状況に応じて過去の経験にとらわれない柔軟な対処(避難行動)が必要
特に、県北部は、40~50年単位で津波被害にあっており、警戒・訓練もしてきたが・・・。県北部では50年前のチリ地震津波を示したポールの存在や、一方、県南部では、先祖の代から「ここまでこない」といった安全意識がかえって避難の足かせ、被害拡大につながった。忘れ物取りに戻った人も。防災教育の難しさを感じた。こちらの方言で「てんでこ」=津波には、それぞれで逃げることが重要。デジタル映像がたくさん残っているので、今後の啓発に使っていきたい。他県にも活用を!
・同報無線の一部で機能不全が発生:ポータブルラジオが有効かと。
防災無線は断線したし、エリアメールはドコモ、DDIの1業者になるうえ発信PCが停電すると機能しない。その点、ラジオは有効、ポータブルラジオ1個、低コストで有効である。
・大規模・広範囲の災害となり、初動においては被災市町の情報収集が困難
・津波で役場庁舎壊滅2町、地震で被災1町=通信連絡手段確保に時間要した。
・多重の通信連絡手段の確保が重要(地上系、衛星系、無線)
県と市町、情報通信システムの補強が必要。衛星無線系は、電源も燃料もすぐに切れてしまった。仕方ないので、時間決めて通話した。燃料と電源を高台に確保しておくべきだった。
・避難所が多数設置されたことにより、避難所や避難者の情報把握が困難
・自衛隊ほか国関係期間、緊急消防援助隊、各都道府県防災ヘリ等による救難、
救助を実施。災対本部事務局でエリア分けを行い連携した取り組みが行われた。
・初動期においては、県内からの物資の確保、被災地への運搬が困難
・避難所や避難者の情報把握が困難なため、物資の必要数量がミスマッチ
どこにどれだけ必要か、わからなかった。地元の情報がつながらず、市町でもわからなかった。
・流通備蓄ではなく、現物の備蓄が重要=住民3日程度、市町村数日程度、県数日程度
・国の現地対策本部が設置され、関西・中部・北陸方面から必要物資を搬送=時間かかる
・搬送手段の確保、及びストックヤード必要、管理=自衛隊、民間の物流業者、倉庫業者の支援が有効
救援物資は、県での集約に数日、市町への配布に数日、と時間がかかった。しかも、大量でさばけなかった。ストックヤードも近県、県内、どこかに必要だった。また、さばく人員(できればプロ)が要。倉庫業界+トラック協会に任せた。市町も、さばけず、クロネコ、佐川にお願いした。
・燃料の不足により、病院、緊急車両、被災自治体、一般住民の活動にも支障発生 1カ月間、市中からガソリン、灯油がなくなる。10Lまでに制限。燃料不足を国に依頼したが、1カ月かかった。山形まで行けば物が買えたのに、そこに行くガソリンがなかった。隣県(山形県)に備蓄が必要。
◎市町村その他現場の状況と課題
・津波・地震による役場庁舎の壊滅(3町)、津波の浸水が引くのに5日
・通信・連絡手段が途絶
・被災が広域におよび、市役所・役場の人間も被災。被災状況がみえにくい仙台市内ですら、10万戸の罹災証明を出した。
・被災地(避難所・避難者数)の情報収集が困難
・避難所が多数設置され、支援対応が困難
・物資の確保が困難
・燃料不足=国への対応を依頼:解消まで約1カ月要した
・県内142ある漁港すべて被災し、水産加工施設もダメに。
・南山陸町を例にとると、一般予算が70億円ほどだが、想定される復興予算は600億円~700億円規模になる。
(2)国の対応の問題
・発災の翌日(3/12)に国の現地対策本部(内閣府をトップに各省庁で構成)を設置。
・物資(食料、燃料、その他)の調達、災害救助法関係の制度運用等の調整を実施
・復旧、復興に向けての情報収集、関係機関における調整も活発に実施
・復旧・復興に向けては財源確保や規制緩和が重要
・国の復興構想会議等で方針が取りまとめられた。
・瓦礫処理や農地の除塩事業など補助率が明確に示されないことが課題
(3)県を超えた広域的対応、協力態勢の課題
・8道県の災害協定(東北・北海道)により応援
・全国知事会や総務省を通じての物資支援や応援職員派遣、大変有り難く、大変有効。
・大規模災害に備え、全国からの応援を調整する仕組みやペアリング支援の検討が必要では!!
いち早く、関西広域連合は入ってくれた。知事会、総務省と県が相談、同じ県、市に入ってもらうよう調整はした。阪神淡路大震災の経験がある関西広域連合とは、被災地が都市型と田園型という違いもあり、初めは戸惑いもあったが、時間とともにわかってもらえた。南三陸町長は大感謝しており、今度、関西が被災したときは東北連合をつくってくれと言っているほど。事前に、支援の環境をつくっておくことが大事だった。
・被災市町からは、市町の職員の派遣要望がある。特に専門職の要請強い。H24年3月までの期限が一つの区切り、その後は要検討か。被災者も同じで、被災市町も自立が必要な面もある。
以上 (報告は、現地でいただいた資料に、聴き取った内容を加えて作成してあります。)
投稿者 boss_blog : 23:19 | コメント (0)
2011年08月05日
山田町から
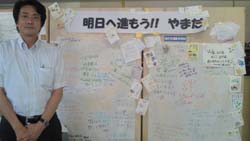
東日本大震災に関する復旧復興支援調査特別委員会の現地調査で、きのうから宮城県と岩手県に来ています。写真は、岩手県山田町の災害ボランティアセンターにて。詳細は、後ほどゆっくり。
投稿者 boss_blog : 12:18 | コメント (0)
2011年07月21日
少々ビビリました・・・ NO.784

※名張駅西口にて
台風一過で晴れ間かと思いきや、今朝は小雨の中での朝立ちとなりました。少しビビリましたね、今回の台風6号。どこかの総理のごとく、居座られたら大変なことになるのではと心配しましたが、雨量のわりには、市内で大きな災害もなくすんだようです。ありがたいことです。
さて、今日は、少し前に調査に出向いた兵庫県の災害対策局での聞き取り(7/12)の内容について報告しておきます。三重県議会では、先に書いたとおり、東日本大震災に関する復旧・復興支援調査特別委員会を設け、三重県の支援のあり方がどうであったか、これからどうあるべきか、を調査しているわけですが、その議論を深めるためには、他県の取り組みがどうなのか、という点が気にかかるところ。鈴木知事のやる気度がマスコミで強調される割には、どちらかというと国の省庁や全国知事会からの要請に基づいて動いているだけで、三重県独自の積極的な取り組みがあまり見えないようです。そこで、先の阪神・淡路大震災の経験から、今回の東日本大震災への支援のあり方が他県とは大きく違うのではと想定し、被災自治体も気になるところではありますが、ここは先にと兵庫県に出向くことにしました。
災害対策局の山田参事様より、丁寧なご説明をいただきました。まず一番驚いたことは、兵庫県自らが被災自治体に頼ることなく、いち早く現地支援本部を立ち上げていることです(静岡県も同様のアクションをしています)。これだけの大きな災害で、しかも、被災自治体の首長や多くの職員が亡くなったり行方不明になっている状況では、「待っていてはニーズはつかめない」「被災自治体に発信能力がない」と想定し、現地で自分たちの足で被災の状況を確認し、すぐさま何が必要かをつかみ対応する取り組みを行っていました(宮城県、気仙沼市、石巻市、南三陸町の4か所に現地支援本部を設置)。関西広域連合としても同様の動きを行っており、現地では、地元の市町や県より、関西からの応援者の方が頼りになったとの声も。結果としてこうした取り組みが被災自治体からは喜ばれたようです。わたしたちも、こうした取り組みを聞くと、今までの概念、すなわち、「現地の受け入れ体制が整うまでは現地に入らない方がいいのでは」という考え方を改めなくてはと思いました。
次に、特筆すべきは、関西広域連合が初めて取り組んだ「カウンターパート方式」(対口支援、ペアリング支援とも呼ばれます)です。連合は、いち早く震災翌々日に委員会を開催し、被災三県に対し、連合の構成府県でカウンタパート(対応相手)を決めて支援することとしました。岩手県には、大阪府と和歌山県が、宮城県には兵庫県、徳島県、鳥取県が支援をという具合にです。支援の行き先がバラバラであった三重県とは、この時点で大きな差があります。兵庫県内の市町も同様の方式をとっています。たとえば、姫路市は石巻市へ、尼崎市は気仙沼市へ、といった具合です。阪神・淡路大震災の被災地、西宮市は、さらに独自の取り組みを行っており、高塚市、川西市、猪名川町と兵庫県阪神支援チームをつくり、被災地に近い宮城県栗原市、登米市と連携し、大きなダメージを受けている南三陸町、女川町を総合的に、長期的に支援する仕組みを整えています。こうしたカウンターパート方式をとれば、医療や福祉、消防や警察、行政支援、それぞれの派遣職員が相互に情報交換が容易になり、刻々と変化する被災地のニーズに対し、よりきめ細かな支援が可能となります。こうした取り組みが今後一層進むことでしょう。
今後の課題として挙げられたのは、やはり被災自治体の職員不足。被災による職員減は否めず、その上、通常業務に加え震災対応業務もこなさなくてはならない状況に、被災自治体からは、市町の応援職員を望んでいます。しかし、一方で、派遣職員をどういう扱いにしていくか、その財政負担も含めて難しい問題もあります。
こうしたお話をお聞きしていると、最近進んでいる災害時の応援協定をある一定の距離間の自治体同士、複数かわしておくことが重要だと再認識させられます。人口規模や地形等は、出来れば似通っていることが望まれます。条件が近ければ近いほど、支援の際にきめ細かな対応が出来ますし、そこでの支援活動が自らの防災施策や街づくりに反映することができるのではないでしょうか。また、津波が予測される沿岸部の自治体を、内陸部の自治体がサポートする仕組みづくりも大切です。わたしたちが住む、ここ伊賀の地は、そうした意味で重要な後方支援の地域になると言えます。今年度から、県の広域防災拠点の整備が県立上野農業高校の跡地で進められますが、タイムリーな整備となりますね。後方支援と言えば、岩手県遠野市が以前から積極的に取り組まれてきた自治体として注目を浴びています。8月には、委員会で東北に調査に入る予定ですが、是非、お伺いしてきたいと思います。以上、報告まで。
蛇足ですが、兵庫県からの派遣人員(市町職員や関係機関職員を含む)は、延べ5万8千人でした(7/8現在)。県職員の派遣で特徴的なのは、県庁の局長クラスを送っていること。現地で仕事がさばけ、なおかつ自分のところの県庁も動かせることが必要だからだそうな。このあたりは、三重県の状況をきちんと整理をして比較する必要がありそうです。

※兵庫県庁災害対策センターにて
投稿者 boss_blog : 23:36 | コメント (0)
2011年07月14日
ちょっと長いですが・・・ NO.782
今年度、ワタシは三重県議会の「東日本大震災に関する復旧・復興支援調査特別委員会」に所属しています。3月11日に発生をした東日本大震災は、激しい地震と巨大津波によって、1万5千人以上の方が亡くなられ、現在も5千人以上の方が行方不明となっている、未曾有の大災害となりました。ライフ・ラインの復旧はもとより、徐々に街の復興に向けて動き出している地域もあるようですが、いまだに10万人近くの方が避難生活を強いられてる状況も続いています。
ワタシ自身も、5月には、地元名張のご当地グルメとして売り出し中の「牛汁協会」の皆さんと一緒に、宮城県塩竃市に炊き出し支援に行ってきました(別掲)。現地の被災状況は本当に激しく、どうやっていけば街が再生されていくのか、想像できない感覚でした。
三重県では、震災発生直後の緊急消防援助隊や広域緊急援助隊(警備部隊)、災害派遣医療チームの派遣から始まり、被災地の避難所支援や応急給水活動など、延べ1500人以上の職員を現地に派遣し、多岐にわたる支援活動を行ってきました。被災地の支援される側も、現地に赴き支援する側も、まさに今まで経験したことのない状況だけに、その支援活動の大変さは想像を絶するものがあります。関係者の皆さまに感謝と敬意を表します。
さて、そんな中、県議会に設けられた特別委員会では、これまでの三重県の支援策が被災地や被災自治体にうまくマッチングしてきたのか、同じく支援に取り組む県内の市町やNPO,民間ボランティアとうまく連携がとれてきたのか、などを検証し、今後の被災地、被災自治体への支援のあり方を提言していくこととしています。
6月8日には、県の関係部局から現在までの支援活動について説明を受け、続く6月22日には、参考人という形で、支援活動に従事されて皆さんのお話を直接聞かせていただきました。以下は、その概略をまとめたものです。
①緊急消防救助隊として赴いた四日市市消防本部の方から
総務省消防庁の指示で当初は千葉県市原市へ消火活動に、その後宮城県仙台市で行方不明者の捜索・救助活動に。千葉のコンビナート火災には、四日市のコンビナート火災対策用の作業車が役立ったようです。まだ、大きな余震や津波の可能性がある段階での活動は、危険を伴うものであり、作業現場への正確な情報伝達が求められます(作業中、5mの津波襲来の誤報があり、緊張が走ったそうです)。
②給水活動に赴いた津市、四日市市、桑名市の水道局の皆さんから
社団法人・日本水道協会からの要請により、宮城県松島町へ給水の支援活動に。地元の消防団の皆さんが道案内をしてくれ、配給には自治会の皆さんが整理券を配るなどして協力をしてくれたようです。一人6ℓとして、配布しましたが、容器もない方があるので、応急給水袋で対応したとのこと。医療施設も断水しており、非常に厳しい環境にあったようです。
③学校緊急支援に赴いたスクールカウンセラー(臨床心理士)の方から
宮城県からの要請を文部科学省経由で受け、気仙沼市の小中学校へ。スクールカウンセラーを経験をした臨床心理士ということで赴く。支援は、学校の日常を取り戻すことのお手伝いで、ケアの対象は学校の先生。子どもたちは場面場面を通じて様子を見るところまで。課題して、心理支援の窓口の一本化の重要性と、マスコミの問題(被災地の先生が取材で子どもたちをさらしてしまったいう思い)を挙げられました。
④「みえ発!ボラパック」を企画してきた「みえ災害ボランティア支援センター」の方から
岩手県山田町に支援センターを立ち上げ、活動中。山田町は岩手県沿岸部で、アクセスしにくいところなので、当初から一番ボランティアの数が少ないため、選んだ。4/1から先遣隊を送り、情報収集と信頼づくりにつとめ、4/28からボランティアを送りこんだ。ボランティアと被災地のマッティング、人の送迎、案内、注意事項の周知、備品の提供などを行ってきた。およそ2年半の支援計画を立てている。課題としては、情報の一元化(同じことをきいてしまう。他のグループの活動がわからないので、調整、連携ができない)。事務スペースが現場にあればいい。会議をやる余裕はないが、同じスペース、もしくは隣にいるだけで情報交換ができる。県内市町のボランティア・センターとの情報交換したいが、まだ未着手。それと、支援する相手先は同じ自治体にすべき。医療、行政、ボランティア、行き先がバラバラでは情報共有できない。これからは仕事の再会、就業の支援、心の復興が必要と思う
→みえ災害ボランティア支援センター
⑤医療救護班を派遣いただいた三重県病院協会理事長から
岩手県と調整し、陸前高田市に派遣することに。三重大学付属病院はじめ県内の公立、民間病院からチームを結成し、ローテーションのもと派遣を行う。赤十字や済生会等は、系列で別途支援に。当初は、被災地へのアクセスにも苦労し、インフラも整わず、しかも、県立高田病院は4階まで津波の被害にあい、カルテも調剤薬局も流されている状況の中、コミュニティセンターに拠点を移し医療活動を行った。帰県したら「チームみえ」としてレポートを提出してもらい情報を蓄積してきた。医療に関わっての課題は、災害救助法から保険診療に切り替わることが問題。厚労省の判断だが。また、現場と県行政とのギャップも問題(現場は、さらなる派遣を求めているが県はもういいと)。まだ支援が求められているが、あと3カ月くらいか。
⑥心のケアチームを派遣いただいた三重県心の健康センター所長から
宮城県、厚労省からの要請で宮城県石巻市へ「心のケアチーム」を派遣。被災地での精神医療や被災者に対する精神的なケアを行う。災害発生時は従来からの患者の症状悪化への対応や急性期への対応が中心だったが、徐々に避難所の巡回や家庭訪問、地元消防などの支援者のケアも行う。課題としては、長期的・継続的な心理的ケアを実施する体制整備。医師、保健師は陸前高田市、心のケアチームは石巻市、やはり一緒の方がよかったのでは。
⑦現地支援調整要員として赴いた県職員の方から
宮城県の災害対策本部に入り、支援のニーズや後方支援のあり方、他県との情報交換などをミッションとした。また、三重県職員の塩竃市等への派遣について、作業状況確認や体調のケアも担う。現地での活動が、6月に県庁講堂で実施した「がんばろう!宮城復興フェア」の実施につながる。
こうしてお聞きすると、いくつかの課題が。まずは、県庁各部局が国の省庁や全国知事会の指示を受け、縦割りで動くので、支援先の被災自治体がバラバラになっていること(市町は全国市長会や全国町村会からの要請)。せっかくの現地で集めた情報が横につながることがなく、生かされません。二つめには、NPOをはじめ多くの市民活動グループが被災地に入っていますが、情報の一元化や情報交換の場が必要です。また、こちらに戻ってきてからの情報交換の場もあればいいかと。医療や心のケアは長期的継続的な支援が求められるにもかかわらず、支援の形が見えません。医療現場は今どこでも厳しい環境にありますが、被災地での支援活動が、その後県内の医療にもプラスになることがたくさんあると思うのですが。今後も、議論を続ける必要があります。
投稿者 boss_blog : 22:12 | コメント (0)
2011年06月21日
御馳走 NO.776
梅雨の晴れ間、議会の合間、と言うことで、今日は地元名張での一日。蒸し暑い一日でしたねえ~。まだ6月が10日あることを考えると、ちょっと辛い?気分に。ではありますが、先日から、少し嬉しいことが。我が家と我が事務所ボスのテレビをようやくデジタルテレビに交換し(今ごろか!?金欠だったので・・・)、あわせてケーブルテレビのSTBもアナログ用からデジタル用に換えてもらった。地元ケーブル会社は、ワタシの前の勤め先であり、営業、工事に来てくれた後輩にイチャモン!?をつけながら、ワイワイと接続工事完了。仕事の手を休めて?ちょっと楽しんでます。まあ、チャンネルがたくさんあっても、そうそう見たいものばかりというわけではありませんが(営業的には、こんなことを言ってはいけません!)、洋楽オタクとしては、見逃せない「ミュージック・エア」が見られるのは御馳走であります(追加メニューですが)。ボスはいつ出てくるかなあ~
きのうは、所属する生活文化環境森林常任委員会の環境森林部所管分の開催でした。治山事業などの肉付けを含んだ約18.5億円の増額補正予算や県政報告書案、産業廃棄物の不適正処理事案、地球温暖化対策の取り組み、県産材の需要拡大に向けた取り組み等について、審議しました。補正予算の中で、県単の治山事業費予算がトータル前年度比91%に落ちているのが気になりました。毎年、地域や市町の要望の積み残しが多いうえに、今回は、県内の防災対策に力を入れる新知事の予算であったはずなのに、この数字は納得がいかないレベルです。今後も、しっかりと要望を続けます。
投稿者 boss_blog : 21:50 | コメント (0)
2011年05月18日
名張へ戻りました NO.769

※桂島の被災状況

※炊き出し作業にも力が入ります

※おいしいと言ってもらえてよかった!

※わたしは配膳係に

※これが「牛汁」です!

※野々島の被災状況

※子どもたちの笑顔に安心しました
宮城県塩竈市(塩釜市)から、帰りも約12時間。今朝7時に名張へ帰ってきました。0泊3日、往復24時間バス移動という強行スケジュールでしたが、参加メンバーの皆さん、本当にお疲れ様でした。到着日の朝から夕暮れまでの限られた時間での活動でしたが、避難所の皆さんには、大変喜んでいただき、また、わたしたちもその笑顔から逆に元気をいただき、有意義な活動が出来たのでは、感じることが出来ました。活動を支えていただいた多くの関係者の皆さんに感謝申し上げます。
名張のご当地グルメとして売り出し中の「牛汁」は、被災地でも好評でした。汁物だけでは頼りないとして最近は、牛汁に伊賀米コシヒカリの焼きおにぎりを中に添えています。「崩して食べるのか、そのままいただくのか」と、尋ねる方もありましたが、伊賀牛をふんだんにいれた汁と焼きおにぎりのコラボはなかなか絶妙で、おかわりの注文もいただいたり。喜んでいただいてよかったです。
今回、被災地の皆さんに元気を出してもらおうと、「隠(なばり)牛汁協会」が炊き出しボランティアにお邪魔したのは、塩竈市の離島である、桂島と野々島の避難所、そして本土の避難所と計3か所。
それぞれ30人~40人の避難者がいらっしゃいます。それぞれの避難所への移動の道中は、あちらこちらで倒れた家やがれきの山が見られ、津波の恐ろしさをあらためて感じさせられました。今回は、視察や調査が目的ではなく、あくまでも支援活動(わたしは牛汁配膳係)なので、あまり情報収集はできませんでしたが、それでも、いくつかお話も伺いました。「そろそろ気温が高くなってきたのに、支援物資の衣料は冬物が多い。夏物がほしい」「島の産業の漁業やノリ養殖に携わってきた人は年齢の高い人が多く、再建できるか心配」「ボランティアの人たちには長期間いてほしい」「でも、これからは自分たちが雇用される公共の復旧事業との住み分けが難しい」などなど。
いずれにしても、瞬間風速的な滞在では、多くのことはつかめませんし、十分なお役にもたちません。また、機会をあらため、少し長めのスパンで支援活動に行ければ行きたいと思います。今回の「隠(なばり)牛汁協会」の活動が、同行してくれた「伊賀タウン情報ユー・YOU」の記者の方によって、同社のホームページに動画掲載されています。お時間のある方は、ご覧ください。
投稿者 boss_blog : 23:09 | コメント (0)
2011年05月17日
桂島、野々島と渡ってきました
桂島と野々島に渡ってきました 津波で家が全壊したり、流出してしまい、長く避難所生活を強いられている皆さんに伊賀名張の新しい名物、牛汁を炊き出し提供してきました。

写真は、塩竃市浦戸諸島、桂島の被災状況です
投稿者 boss_blog : 15:35 | コメント (0)
2011年05月16日
震災支援のため宮城県へ
東日本大震災の被災地支援のため、宮城県に向かってます なかなか長期のボランティアは難しいと思っていたところに、名張の牛汁協会が炊き出し支援に0泊3日で宮城県に行くと聞き、わたしも会員なので同行させてもらうことに。12時間かけてバスで走ります。明朝には塩竃市に着き、船で二つの島に渡る予定です。足手纏いにならぬよう、頑張ります。
投稿者 boss_blog : 18:37 | コメント (0)
2011年05月11日
3.11から2か月 NO.765
時折激しい雨が降ってきます。知らない間に台風まで発生していますね。いつの間にか、春から夏へと季節は動いています。そんなワタシの今日のカーライフのお伴は、久しぶりにオアシスの「ヒーザン・ケミストリー」。一応、オアシス・ファンなのですが、09年に活動停止していたとは、知らなんだあ~。「ソングバード」と「リトル・バイ・リトル」は、何とも心地よいであります。
さて、東日本大震災から、今日で2か月になりますね。現地に出向いてない身としては、あまり何も言えないところがありますが、テレビや新聞を通して伝わる情報だけでも、何とも辛い気持になります。死者、行方不明者、合わせて2万5千人近くにのぼっています。この数字自体、想像がつかないものですが、そのひとり一人に、地震や津波が襲う直前まで、それぞれの人生があり、震災がなければそのまま続いているはずの人生があったわけで、その悲しみ、、無念さを考えると言葉になりません。今、わしたちに出来ることは、その地域に残った人々が、なんとか頑張って暮らし続けられるための支援を行うことしかありません。今、県議会は、役選や今年度の委員会体制を調整しているところですが、東日本大震災の復旧・復興支援のための調査特別委員会ができる見込みです。ワタシも委員として参加の予定で、被災地への県の支援の在り方や、県内の震災にかかる経済的影響等について、しっかり調査したいと思っています。
投稿者 boss_blog : 23:04 | コメント (0)
2011年05月07日
GWも終わりに NO.763
GWも終わりに近づきつつありますね。もうとっくに仕事してる!という人も多いかと。気持ちを切り替えて、がんばりましょ。このGWに東北の被災地にボランティア活動に出向いた人もいらっしゃるでしょう。会派新政みえの仲間の何人かも、この機会に行っている模様。ワタシも、タイミングと活動内容とをリサーチしながら思案中であります。なんとかお役にと思いながらも、しかし、長い期間の滞在は難しいという、あまり喜ばれないボランティア(志願兵)であります。いい方法があれば、教えてください。
浜岡原発の停止を菅首相が中部電力に要請したニュースは衝撃的でした。東京電力の計画停電の話を「大変やなあ」と他人事のように聞いていたワタシも、わが身のこととなるやもと危機感いっぱいに。浜岡原発は、1期目の時代に中部電力さんの案内で視察させてもらった。東海地震のこともあり、当時から、地震や津波の対策には万全を期している旨の説明を聞いた記憶が。今後30年以内にM8程度の地震が発生する可能性が87%と示されている東海地震を考え、新たな防潮堤の設置などの対策が講じられるまでの間ということのようですが、中部電力さんの対応が注目されます。地域経済への影響など、十分な検討が必要なのは言うまでもありませんが、専門家ではなくとも、この機会にワタシたち自身が真剣にエネルギー問題について考える必要があると思います。
投稿者 boss_blog : 21:02 | コメント (0)
2011年03月05日
広がりませんように NO.758

選挙が近付くにつれ、なかなか更新が思うようにまかせませんねえ。自分の要領の悪さにホトホト情けなくなります。今日は午前中、防災農水商工常任委員会・分科会で来年度予算等の審議を行ったのち、午後からは、高病原性鳥インフルエンザが発生した南伊勢町に委員全員で出向き、殺処分や埋却作業が行われている現場の視察調査を行いました。24時間体制(作業員のべ2,600人。夜中も交代で作業に従事)で、県職員、町職員の皆さんはもとより、自衛隊をはじめ多くの皆さんの協力を得て、対応にあたっていただいたお陰で、約24万羽規模の大量処理もスムーズに進みました。お疲れ様です。今後、県内においてさらなる発生がおこらないよう願うばかりです。先般の紀宝町よりはるかに規模が大きい今回の事案でしたが、同規模同等もしくはそれ以上の養鶏場は、県内に17農場もあり、発生時の作業体制の事前構築も必要かと感じました。
投稿者 boss_blog : 00:04 | コメント (0)
2011年01月12日
凍結に気をつけて! NO.747

※百合が丘サークルK前交差点にある郵便ポストが無残にも・・・。今朝の道路の凍結で、誰か車をすべらせてしまい、ぶつけたのかな?
今朝も少し積雪がありましたね。寒波がなかなか緩みません。積雪は、わずかだったものの-3度の気温でうっすら積もった道路の雪が凍結、市内のあちらこちらで車の事故が多発したようです。この冬は降雪が多く、みなさん気をつけられていると思いますが、今朝のように積雪量が少ないと甘くみてしまいます。外気の気温も十分注視し、凍結がらみの事故に気をつけてくださいね。
投稿者 boss_blog : 11:40 | コメント (0)
2009年10月08日
かなり被害が出ました NO.674
台風18号の襲来で、名張市内でも多くの被害が出ました。けが人等がでなかったのは、幸いですが、市内のあちらこちらで、床下浸水や崩落が発生し、市民生活に影響がでています。あの伊勢湾台風からちょうど50年の節目の年に襲来した台風18号。あらためて、自然災害の恐ろしさを感じ、そして、防災対策向上の必要性を思いました。
市内の被害状況(8日午後2時)
倒木17件、土砂崩落等18件、床上浸水1軒、床下浸水19軒、道路冠水13件、道路損傷2件、田畑冠水10件、田崩落69件、家屋崩壊1軒、家屋損傷1軒

瀬古口区での浸水、住宅街が一面川のようです

床下浸水の家屋、畳の下はプールのように(瀬古口区)

浸水のあとが、くっきりと。後片付けも大変です(赤目町柏原区)

赤目中学校近くの宇陀川は、道路にまで溢れてしまいました。警戒水位を越えた名張川も心配でしたが、ダム等の調節もあってか、何とか持ちこたえてくれたようです。よかったです。

県道赤目滝線が、道路下部の崩落(赤線で囲まれた部分は、下が空洞状態)で、またまた通行止めに。秋の行楽シーズンへの影響が心配です。何とか、仮復旧を施したいところ。

錦生地区の竜口での崩落現場。また、薦原地区、緑が丘区では長時間にわたって停電が発生していました。

市役所の職員の皆さんも、市民の生命・安全を守るために、徹夜で頑張ってくれていました。お疲れ様です!
投稿者 boss_blog : 22:00 | コメント (0)
2009年01月10日
アンシンダーLも登場 NO.610

本日は、朝から名張市消防団の消防出初め式へ。昨年から、会場が名張小学校の運動場から夏見の体育館に変更されたので、この寒さも気にならず、ありがたい環境に(そう言えば、一昨年は確か猛吹雪の中であったような記憶が・・・)。

119団アンシンダーも、啓発の応援に。

アンシンダーLも登場(Lはレディーということだそうな)。ワタシは、初めて見させていただきました。女性消防団のメンバーの方が、担当されているそうな。今年も、市民の安全、安心のために大いに頑張ってほしいと思います。
投稿者 boss_blog : 21:07 | コメント (0)
2008年11月30日
か・な・り・高い確率 NO.591
今日は朝から赤目地区防災訓練に参加させていただきました。寒風の中での訓練でしたが、皆さん、熱心に取り組んでられました。今後、30年以内に起こる巨大地震の確率は、東海地震が87%、東南海地震が60~70%、南海地震が50%といわれています。か・な・り・高い確率と言えますが、感覚的に染み込まないところが困ったものです。ネットでおもしろい比較の数字がありました。今後30年以内に交通事故で死亡する確率は0.2%、交通事故でケガをする確率は20%だそうな。目の前で現実にくり拡がられている交通事故は我々認識できるので、シートベルトをつけたり、エアバッグをつけたり、交通安全のお守りを買ったりと、気にしますが、確率的にかなりヤバイ地震には無頓着?という変な感じに。こういう機会に、あらためて防災の意識を高めたいものです。
本日の主な日程

※赤目地区防災訓練(赤目小学校)

※百合小・赤目中「私たちの町」絵画展(パークシティ)

※名張市立学校美術展覧会(桔梗小体育館)

※第10回れもんぐらすコンサート(美旗公民館)

※第4回文化力シンポジウム(サンピア伊賀)
投稿者 boss_blog : 18:58 | コメント (0)
2008年06月15日
岩手・宮城内陸地震 NO.493
岩手・宮城内陸地震、被害の大きさに驚きました。亡くなられた方のご冥福を心からお祈りするとともに、負傷された方の早期回復、行方不明の方の無事救出をお祈りします。今回も断層のズレによるものと言われています。あまり、専門的なことは、わかりませんが、報道によれば、震源地に近い断層は、30年以内の地震発生確率が0%であったとのこと。活断層による直下型地震の予想の難しさと、影響力の強大さをあらためて感じました。この伊賀地域にも、断層が存在することもあり、建物の耐震化が急がれます。戸建の住宅にしても、避難所となる公共施設にしても、地震対策の遅れは、かなりひどい状態。啓発もさることながら、補強工事への支援充実が急務です。特に、補助基準のハードルの高さ(耐震診断評点1.0以上に達する補強工事のみ)は、ぜひとも再考してほしい。
投稿者 boss_blog : 23:06 | コメント (0)
2007年07月14日
台風接近中!! NO.278
台風4号(マンニィ)が接近しています。沖縄、九州、四国と、台風が通過するに従って被害が広がっているようです。三重県、そして、名張には明日の未明から早朝にかけての接近か。大きな被害が出ないことを祈っています。朝から、夕方までは選挙関係の作業が続きましたが、夕方からは、台風の接近に備えて自宅の周りを整理整頓。一段落してから、河川の状況を見回り、その後、直近の状況確認に市役所を訪問した。
20時現在、市内では、大きな被害はない模様(鴻之台で、側溝からあふれた水が店舗に入ったという被害が一部あったよう)。この時点で、県内では伊賀だけが警報がだされていないという希な現象に。全国各地で降雨量が数百ミリに達しているところが多いが、こちらはお陰で若干少なめ。ちなみに名張は、0時-20時の間、総雨量60.5ミリという状況。時間雨量は17時台が最高で、15ミリという状況だ(危機管理室より)。もちろん、雨も風もこれからという段階。また、河川増水は、名張市内より上流の奈良県側の雨量が大きく影響する点も考えておかなくてはならないそうだ。市長や副市長、収入役、各関係部局の職員さんも、みんな参集していて、これから明日昼ごろまで、庁舎内で待機されるよう。お疲れ様です。
みなさんも、十分気をつけてください。家の周りは今のうちに整理を。台風が接近してからは、外に出ないようご注意を。(追記 22:52現在 伊賀地域に大雨・洪水・暴風警報発令中)

※午後7時の名張川の様子。鍛冶町橋付近。3つのダムから一斉に放流されているので、どの場所も猛烈な勢いで流れています。

※そんな危険な川の近くで、川の水を採取する作業中の人たちを発見。尋ねてみると、国土交通省から委託されて、増水時の川における土砂の流出状態をサンプリング(流送土砂調査と言うらしい)しているとのこと。大変な作業です。お気をつけて、お疲れ様!
投稿者 boss_blog : 21:24 | コメント (0)
2007年06月26日
ブログをやめてしまった!? NO.266
ブログをやめてしまった!!・・・のでは、ありません。ちょいと、忙しすぎただけであります。「継続は力なり!」とは、なかなかいきませんなあ・・・。まっ、こういう時はいつもの手で、そう、写真報告で済ませちゃいましょう!
6/22
・教育警察常任委員会に出席 そう、新聞掲載のとおり、「もめました」ねえ。こういう時の委員長は、つらい。ネタは、警察署の整備問題。今回、唐突に補正予算で鳥羽警察署と津南警察署の整備費が計上されたきた。特に津南警察署については、県久居庁舎を利活用する案だが、旧の久居建設事務所やこころの健康センター等が今もこの久居庁舎には入っている。引き上げや移転については関係機関で調整合意済みというが、県民や県議会には何ら説明された形跡がない。両署とも老朽化、狭隘、耐震に問題ありと、その整備については全く異論はない。 しかし、内向きの合意形成はあっても、外向きの合意形成は全く皆無。その点については、執行部側も認めているにもかかわらず、補正予算案はそのまま通したい意向。「行政内部の決定に間違いはない。よって県民及び議会は文句を言わずついてくるべし」的発想がみえる。それは、ちょっと違うのではと異論が出た。賛否が拮抗しそうだったので、採決の可否を先に問うたが、これも4:4。結果、わたくし委員長が採決しない方向を選択し、予算決算常任委員会の場での採決に委ねることとなった。その夜は、該当委員会の執行部のみなさんとの、ハツコン(初懇)と議会では呼ばれる懇親会に出席。教育委員会のみなさんはニコニコしていただいていたが、県警のみなさんは一様にカタイ?表情。これも役目ですからお許しを・・・。ちなみに、明日27日が予決常任委員会の日でございます。
6/23

三教組名張支部定期大会(桔梗公民館)に出席。少人数教育や伊賀の高校再編活性化問題、教育改革推進会議等、喫緊の課題について挨拶を兼ねて皆さんにご報告。

我が会派「新政みえ」の県政報告会を紀北町海山会館で開催。こちらも、先日同様遠かったあ~。でも、何があっても、万障繰り合わせて会派のみんなが結集する。そして、準備から来場者のお出迎えまで、みんなで協力し合う。この結束力が我が会派のエネルギー源でもある。玄関に立つスーツ姿のおっさん連中が我が会派の仲間たち。ちょっと、ヤクザの出入りっぽかったけど・・・
6/24

名張青年会議所創立45周年記念式典に出席(パーム・ド・夢)。なかなか豪勢な式典でございました。来賓あいさつでは、ぜひ、みなさんの手で道州制の勉強会を地域で立ち上げてほしい旨をお願いした。ゲスト講演には、元近鉄バッファローズの有田修三氏が来られていた。元近鉄ファンとしては、じっとしていられず名刺交換をさせてもらう。「感激!」であります。
6/25

早朝より、近鉄名張駅前にて、高橋千秋参議院議員と朝立ち。とにかく選挙が目の前に迫ってくると、どうしても忙しくなる。朝晩を含め、やたらと打ち合わせや会議の連続。なかなか自分のペースがつかめません。でも、それはともかく、千秋さん、頑張って!! (・0☆)

観光カリスマの山田桂一郎さんの講演会に参加(アスピア)。予想を上回る内容のおもしろさ、ウンチクに、感動!! 目から鱗モノの話がワンサカ! メモをとりまくったので、後日、ゆっくりご報告を。
6/26
今日は、書類整理や選挙がらみの仕事やらと、忙しく過ごさせていただきました。以上、ご報告まで。
投稿者 boss_blog : 21:54 | コメント (2)
2007年04月21日
ワタシは、参加しておりません・・ NO.222
あいさつまわりをはじめ、まだまだ選挙関係の後始末が終わりません。本日は、名張市子ども会連合会の総会に出席。それ以外はバタバタとしております。
昨日の、会派主催の三重県中部地震の災害調査会。いろいろ勉強になりました。一番は、やはり行政職員の参集(登庁)の問題。それぞれの行政職員の何割が参集したかが、マスコミで取り上げられていますが、参集の基準(震度によって誰がどこまで登庁するか)の周知徹底があらためて必要なようです。それと、各々の職員との連絡の困難さが浮き彫りに。携帯がつながらないとわかっていても、それに頼ってしまっていることがあらためてわかった。
非常時に強いメールの活用が望まれるのと、せめて県内の行政職員は、「防災みえ」のメール受信は義務付けておいて欲しいもの。各地の震度くらいは、メール配信で確認できるので、あとは定められた基準に従って自らの行動を自己判断すればいいだけだ(ちなみに今回の地震後、「防災みえ」の登録が2,000件くらい?増えたそうな。いい傾向です)。今回は、あまり問題とならなかったが、交通規制のシュミレーションなんかも、重要な要素だと言う意見があった。耐震診断や耐震補強の促進も、もちろん大事だ。
今回は、幸いなことに被害が少なくてよかったのですが、被害が甚大な際に、近隣の府県や市町村の支援をお互いが受けやすくするために、災害時の情報収集や提供のシステム(たとえば、ホームページでの災害状況のお知らせや相談窓口の案内、各種手続き等々)を共通化しておくことによって、他の自治体からきた応援部隊が即、協力できる体制にしておくことが有益だと言ってきましたが、こういう点についての取り組みが全国的に進んでいるものなのか、また、一度確認してみたいと思います。
このタイミングを生かして、さらに地震対策を進めていくべきと思いますねえ。それにしても、近隣の某市長さんが大きく話題に・・・。ワタシまで、参加者の一人ではなかったかと、たずねる人までいる。ワタシは参加しておりませんので、念のため・・・。
投稿者 boss_blog : 22:53 | コメント (0)
2007年01月17日
願望・・・ NO.155
ブログのアクセス件数について、えらそうに?書いておきながら次の日はサボですか!いけませんな~ (^^ゞ これだから政治家?は信用できない。すみません m(_)m きのうは、夜の会合で飲み過ぎてしまいました。会合の冒頭あいさつで、「今日は後に予定をいれてませんので、ゆっくり、みなさんと懇談したいと思います」などと言ってしまったのが、間違いの元。注がれるお酒を拒めず・・・深酒に。反省であります。

きのう今日は、選挙の関係もあって、市内各所をご挨拶にまわらせていただいた。いつもお会いさせていただく顔もあれば、ひさかたぶりにお会いする顔もあり、自分の怠慢を大いに反省させられる。夜は、会合が続きます。昨夜は、宅建協会名張支部さんとの懇親会、今晩は、UIゼンセン同盟さんの新年交流会(津)に出席。あまりお酒は強い方ではありませんので、すぐ眠くなってしまいます。写真は、ワタシの今の願望!?我が家のリョウちゃんの寝姿ですが・・・一度ゆっくりとこんな風に昼寝してみたい(4月までは無理か)

※UIゼンセン同盟さんの新年会では毎年剣舞を披露いただく。ちょっと珍しい!?

※同上
今日は、阪神淡路大震災のあった日。ワタシは、名張の震度4を感じただけですが、あのヤバイ揺れの感覚は今でも忘れない。この地域で心配される東南海・南海地震の発生確率は、今後30年以内に40%、さらに50年以内には80%と予測されている。 また、地震の規模は、東南海地震と南海地震が同時発生した場合、M8.5前後になるそうだ。日ごろから、十分な備えを心掛けたいもの。三重県では、「防災みえ.jp」というホームページで防災情報を提供(メール配信)している。ワタシは、ケイタイにも登録してあるので、常に警報等の情報がはいってくる。ぜひ、みなさんも登録して活用してください!亥の年は、大災害が多い年だそうな。1923年=関東大震災、1959年=伊勢湾台風、1995年=阪神淡路大震災、他にもまだあるらしい。因果関係があるとは思えませんが、十分気をつけたいですね。
PS.1/15付けの朝日新聞社会面の震災シリーズには泣けました。命はホント大切にしたい。
投稿者 boss_blog : 21:56 | コメント (0)
2007年01月09日
初体験の「視閲式」 NO.149
本日は、朝から「三重県警察年頭視閲式」に参加した。選挙活動に励まねばならない大事な時期ではありますが、教育警察常任委員会副委員長でもあるし、また、こんな機会にしか視閲式を見れる機会がないかもというミーハー的な思い(関係者の皆様には失礼な言い方ですが)も重なり、出席してしまいました。



初めて見せていただきましたが、なかなか迫力のある、すばらしい式典でした。様々な部隊や多様な特殊車両なども見せていただき、来てよかったと。刑法犯の認知件数は減ってきているものの、凶悪犯罪等の影響か、県民の体感治安はよくありません。こうした式典も、もっと多くの県民に見ていただけると、安心感につながっていくのかも知れません。
投稿者 boss_blog : 20:52 | コメント (0)
2006年12月29日
今年の年末警戒は・・・ NO.141
明日は、もう晦日。2006年、平成18年も残りわずかだ。そして、遂に来ました!“雪”であります。こんな寒い日は、体はもちろんのこと、心もあったかくしたいもの。そんなワタシの今日のカーライフのお供は、サベージ・ガーデンの「affirmation」。サベージ・ガーデン!?懐かしい!と言われる方もあろうかと。オーストラリア出身のデュオで、94年から01年まで活躍した。シドニー・オリンピックの閉会式で熱唱していたのが記憶に新しい。中心人物のダレン・ヘイズは、現在一人で活動している。「affirmation」は99年の作品、3、5、12曲目は必聴です。
本日は、午後10時から、名張市消防団の「年末特別警戒」の巡視に、亀井市長をはじめ関係者のみなさんとともに参加。各地域で警戒にあたってくれている消防団のみなさんを激励してまわる。約2時間かけて、錦生、赤目、箕曲、国津の4分団を廻った。つい、2~3日前まで、暖冬だったのに、どうしてこういう日に限って、寒波となるのか・・・。やっぱ、ワタシの日頃の行いでしょうか・・・。
現場では、亀井市長、松崎市議(総務企画委員長)、ワタシ、渥美名張警察署長の順に、激励のあいさつをするのですが、なにしろ、時間も時間、そして、この厳しい寒さ。いかに短く、ごあいさつするかが、最大のポイント!?であります。いずれにしても、各地域の団員のみなさま、本当にご苦労様でした。

事務所に戻って、ブログを書いていますが、少し気になることが・・・。昨年、一昨年と、ちょうどこの年末警戒の巡視が終わってから、火事が起きている。昨年は、旧町の新町、愛宕神社の社務所が焼けた。偶然のこととは思いますが、何か因縁めいたものでも・・・?。とにかく、何も起こらないことを祈って、これから家に向かいます。おやすみなさい!
PS.年末警戒でがんばっていただいている消防団のみなさんの写真を掲載する予定でしたが、携帯カメラの調子が悪く、いい写真が撮れませんでした。ごめんなさい。写真が入らないブログが続くのも寂しいので、内容に関係ないですが、我が家の住人二人の写真を。以前に、紹介済みのリョウちゃんとソフィーちゃんです。
投稿者 boss_blog : 23:59 | コメント (2)
2006年10月14日
体に秋がしみこむ NO.79
きのうも堅い話ばかり書き過ぎたような。しかも、長い!(誰があんな長いもんも読むか(― ―‘)お叱りを)。今日は、軽くいきたいところ。まずは、久しぶりに音楽の話しから。今日のカーライフのお供は、スティングの「テン・サマナーズ・テイルズ」。秋は、やっぱスティングです。稲刈りは、終わっちゃったけど、金色に輝く田園風景を眺めながら、スティングの「フィールズ・オブ・ゴールド」なんぞを聞いた日にゃ、体全身が紅葉するがごとく、体に秋がしみこむ。みなさんは、秋を堪能してますか。そろそろ、松茸がおいしい季節でもあり・・・と、口にははいりませんが。
さて、きのうの教育警察常任委員会の報告をさらりと。以下の議案と請願を可決・採択しました。
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
・「三重県営鈴鹿スポーツガーデンに人口芝敷設について」の請願
・「学校安全法(仮称)の策定をはじめとする総合的な学校の安全対策を求めることについて」の請願
・「30人学級を柱にした義務制、高校次期定数改善計画の策定、教育予算拡充を求めることについて」の請願
・「義務教育国庫負担制度の存続および更なる充実を求めることについて」の請願
併せて、警察からは
・県の総合計画である「県民しあわせプラン」の第2次戦略計画について
・警察職員定数と人員配置について
・交番・駐在所の再編について
・警察職員の研修について
・犯罪情勢、交通事故情勢について
教育委員会からは
・県の総合計画である「県民しあわせプラン」の第2次戦略計画について
・三重県における特別支援教育の推進について
・平成20年度三重県立高等学校入学者選抜の実施等について
・平成19年度三重県公立学校教員採用選考試験の結果について
・指定管理者制度導入の進捗状況について
ほか9項目
の説明があり、それぞれ審議した。警察本部へのワタシからの注文は、地元箕曲駐在所廃止の件もあるので、交番・駐在所再編に係る地元への説明責任を果たすこと、特に、廃止後の状況報告をきちんとするよう求めた。
この件については随分長い間、県警には言いがかり?をつけてきた。駐在所を廃止して交番を充実させるというものの、人は増員になるでなく、パトロールが強化されると言うものの、具体的な強化策を訊くと犯罪抑止に影響するからと逃げられる。結局、ちゃんとやるから信用しろ、というレベルでしかなく、こちらとしては、住民に説明責任が果たせない。ならば、結果で判断するしかない。区域内の刑法犯認知件数が、統合再編以降、下がるという結果を頂戴するしかない。経緯を見守りたい。